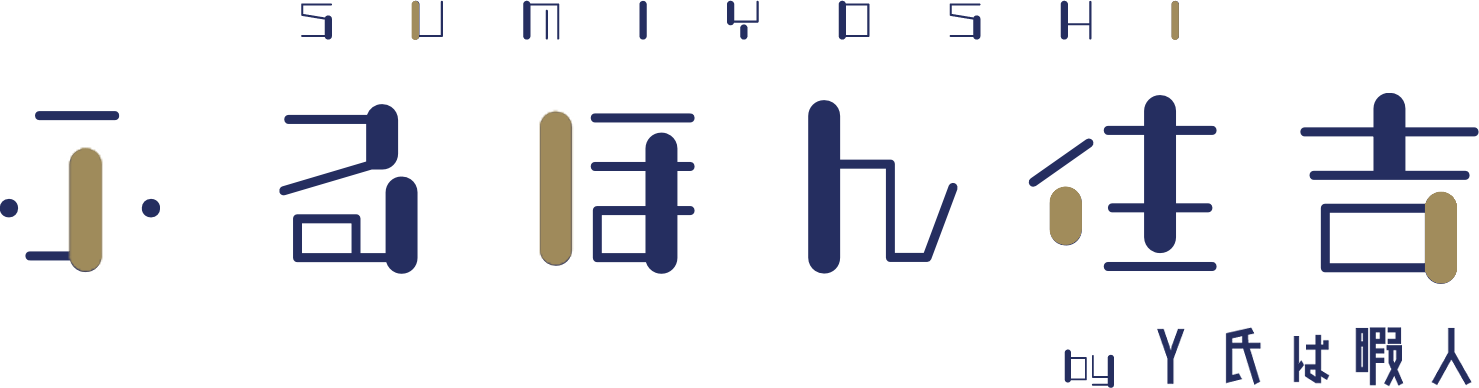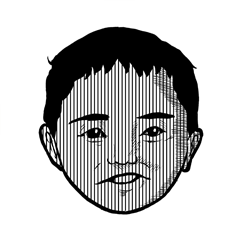【邪馬台国はどこにあった?!】魏志倭人伝を小学生でもわかるように解説 2/2

【邪馬台国はどこにあった?!】魏志倭人伝を小学生でもわかるように解説 2/2 です。
前回、邪馬台国までの道のりを魏志倭人伝にしたがってたどってみました。はたして邪馬台国は九州のはるか南にあったのでしょうか??
前回の記事をまだ読んでいない方はまずはこちらをどうぞ→【邪馬台国はどこにあった?!】魏志倭人伝を小学生でもわかるように解説 1/2
ところで、魏志倭人伝には当時の倭(日本)の人々がどんな様子だったかも記されています。ちょっと話はそれますが、ついでなので日本にはどのような人たちが住んでいたのかを見てみましょう。
服装・身なり
・男性も女性も、大人も子供も、偉い人も民衆もみんな顔や体に刺青(いれずみ)をしている。その刺青(いれずみ)は階級によって入れる場所や大きさが違う。刺青(いれずみ)はおまじないの意味もある。
・はちまきをつけて布を体に巻いている(真ん中に穴の空いた布に頭を入れて結んでいる)。
・みんな裸足で生活している。
・顔に赤い顔料を塗る(化粧?)。
・矛(ほこ)、楯(たて)、木でできた弓を使っている。
食べ物
・海に潜って魚や貝をとっている。
・一年中生野菜を食べている。
・竹や木でできた器に入れた食べ物を手で食べている。
風習
・人が死ぬと土を盛って塚を作る。その後十日間ほどは肉を食べない。遺族の代表は泣き明かし、それ以外の人はお酒を飲んで歌い、踊る。葬った後は家族で禊(みそぎ=川や海の水で体を清める)をする。
・中国に使者を送るときには持衰(じさい)を立てる。持衰は体を洗ったりせず、肉も食べず、婦人を近づけず、という状態にさせる。使者の旅がうまくいけばご褒美を与えるけれども、暴風雨などで旅がうまくいかなかったら殺されてしまう。
・長寿で百歳ぐらいまで生きる
・偉い人は4〜5人の奥さんがいる。偉い人でなくても2〜3人の奥さんがいる。でもヤキモチやきではない。
・盗みなどの犯罪は少ない。軽い犯罪の場合は家族が奴隷にされてしまう。重い犯罪の場合は家族が滅ぼされ、親戚にも影響がある。
その他にも真珠が採れることや、占いをしていることなど色々と特徴が書かれています。

さて、話を戻します。邪馬台国はどこにあったのかを再び考えてみます。
邪馬台国の場所については北部九州説と畿内説(近畿地方説)の2つがあります。
それぞれの主張はこんな感じです。
北部九州説
・魏志倭人伝に書かれているものに似た特徴の棺がたくさん見つかっている。(↓ こんなもの)

・「水路を二十日」「水路を十日、陸路を一月」という表現(前回記事を参照)はスタート地点(韓国あたり)からの合計距離であると考えると矛盾しない。
・「末盧国(まつろこく、もしくは まつらこく)」「伊都国(いとこく)」「奴国(なこく)」などはほぼ間違いなく九州にあった国なので、邪馬台国もこの付近にあったはず。
畿内説(近畿地方説)
・魏志倭人伝に倭の女王に100枚の銅鏡をプレゼントしたと書かれていて、近畿地方では九州よりも多い数の大量の銅鏡が見つかっている。
・魏志倭人伝に書かれている方角に誤りがあり、水路を南に二十日を東に二十日に訂正すると、ちょうど瀬戸内海を通るようなルートになり、合致する。
・邪馬台国が、近畿地方に4世紀頃に登場する大和朝廷とつながっていると考えると自然である。「ヤマタイ」と「ヤマト」も似ている。
・
・
・
・
う〜ん、どちらの説ももっともらしくてなんとも言えない感じですね。
ではちょっとここで魏志倭人伝の中で気になる文章をピックアップしてみたいと思います。(※文章は「魏志倭人伝|邪馬台国の会」より引用しています)
つぎに斯馬国(しまこく)がある。
つぎに已百支国(いわきこく)がある。
つぎに伊邪国(いやこく)がある。
つぎに都支国(ときこく)がある。
つぎに弥奴国(みなこく)がある。
つぎに好古都国(をかだこく)がある。
つぎに不呼国(ふここく)がある。
つぎに姐奴国(さなこく)がある。
つぎに対蘇国(とすこく)がある。
つぎに蘇奴国(さがなこく)がある。
つぎに呼邑国(おぎこく)がある。
つぎに華奴蘇奴国(かなさきなこく)がある。
つぎに鬼国(きこく)がある。
つぎに為吾国(いごこく)がある。
つぎに鬼奴国(きなこく)がある。
つぎに邪馬国(やまこく)がある。
つぎに躬臣国(くじこく)がある。
つぎに巴利国(はりこく)がある。
つぎに支惟国(きくこく)がある。
つぎに烏奴国(あなこく)がある。
つぎに奴国(なこく)がある。
これは、女王の境界のつきるところである。
▲ 邪馬台国から奴国(なこく)に至るまでの国を順番に書いたものです。奴国(なこく)で女王(国)の境界がつきると書かれています。ここではおそらく女王=倭(わ)という意味で書かれていると思われます。
一支国(いきこく)や末盧国(まつろこく、もしくは まつらこく)、伊都国(いとこく)などは現在でいうところの市町村ぐらいの大きさしかありません。なので、ここに並べられている国も市町村ぐらいの大きさのものだと思われます。
もし近畿地方から市町村ぐらいの大きさを並べていったら、100個ぐらいの数が必要になるはずでが、魏志倭人伝の文章では邪馬台国から奴国(なこく)までが20個ぐらいの国で収まっています。
そもそも、魏志倭人伝には30個ぐらいの国が倭(日本)の中にあったと書かれていますが、市町村ぐらいの大きさの国が30個だとしたら北部九州ぐらいで収まってしまいますね。

▲ もう一度 奴国(なこく)の場所を確認してみましょう。奴国(なこく)は福岡県北部でほぼ間違いないと考えられています。漢委奴国王印(金印)も福岡の志賀島から出土しています。「境界のつきるところ」ということは、

▲ こういう感じで南からや東から国を並べていくと奴国(なこく)で「境界がつきる」並びにすることができますね。
奴国(なこく)の西側には伊都国(いとこく)や末盧国(まつろこく、もしくは まつらこく)がありますし、北側は海ですので南〜東の方角から順番に書いていると思われます。
女王国より以北には、とくに一大率(ひとりの身分の高い統率者)をおいて、諸国を検察させている。諸国はこれを畏れ憚っている。
(一大率は)つねに伊都国に(おいて)治めている。国中において、(その権勢は、中国の)刺史(郡国の政績、状況を報告する官吏。州の長官をさすばあいもある)のごとき(もの)である。
▲ そして、こちらの文章。
難しく書かれていますが、要約すると、「女王国(これは邪馬台国の意味だと思われます)より北側の国は伊都国から派遣された調査員が各国を監視している」という内容のようです。

▲ もし近畿地方に邪馬台国があったとするとこんな感じになります。これだと、どうしても違和感を感じます。すぐ近くの奴国(なこく)や末盧国(まつろこく、もしくは まつらこく)は伊都国(いとこく)の調査員が監視をしていないということになってしまいます。

▲ もしこのレイアウトだとしたら自然だと思います。
女王国の東(方)に、千余里を渡海すると、また国がある。みな倭 種である。
▲ 次にこちら。女王国(これは邪馬台国の意味だと思われます)の東に海を渡ると、そこにも倭(わ)の人が住む場所があると書かれています。もし九州だとしたら海をわたるとまた中国地方た四国があるので倭(わ)の人が住む場所があるというのは自然です。近畿地方は東の方までずっと陸続きです。
その南に狗奴国(くなこく)がある。男子を王としている。 その官に狗古智卑狗(菊池彦か)がある。女王に属していない。
▲ 邪馬台国の南に倭(わ)に属していない狗奴国(くなこく)があって、狗古智卑狗(くこちひこ、くこちひく)という官がいると書かれています。一説によると、狗古智卑狗(くこちひこ、くこちひく)は熊本で後に大きな力を持つ菊池氏につながる一族だと考えられています。そして、狗奴国(くなこく)の「くな」と熊本の「くま」も似ています。
それを信じるとすると邪馬台国は熊本の北側にあったことになります。
さらにさらに、魏志倭人伝以外の文書になりますが、隋書倭国伝という、魏志倭人伝より少し後の倭(わ)について書かれた文書にこんなことが・・・
有阿蘇山、其石無故火起接天者、俗以為異、因行禱祭。
▲ 阿蘇山が噴火したら人々は異を以って(良くないことが起きる前触れとして??)祈祷をすると書かれています。やっぱり、倭(わ)は九州のこととして認識されているような気がしてなりません。
そして、もう一度↓この一文を見て下さい。
つぎに斯馬国(しまこく)がある。
つぎに已百支国(いわきこく)がある。
つぎに伊邪国(いやこく)がある。
つぎに都支国(ときこく)がある。
つぎに弥奴国(みなこく)がある。
つぎに好古都国(をかだこく)がある。
つぎに不呼国(ふここく)がある。
つぎに姐奴国(さなこく)がある。
つぎに対蘇国(とすこく)がある。
つぎに蘇奴国(さがなこく)がある。
つぎに呼邑国(おぎこく)がある。
つぎに華奴蘇奴国(かなさきなこく)がある。
つぎに鬼国(きこく)がある。
つぎに為吾国(いごこく)がある。
つぎに鬼奴国(きなこく)がある。
つぎに邪馬国(やまこく)がある。
つぎに躬臣国(くじこく)がある。
つぎに巴利国(はりこく)がある。
つぎに支惟国(きくこく)がある。
つぎに烏奴国(あなこく)がある。
つぎに奴国(なこく)がある。
これは、女王の境界のつきるところである。
▲ 阿蘇山の「蘇」という字が3回も!これは偶然でしょうか?!阿蘇山は大きな山です。3つの国にまたがって名前が使われてもおかしくはないでしょう。
まとめ

では邪馬台国はどこにあったのでしょうか??これまで見てきたものをまとめるとこんな感じです。

▲ このあたりの位置ならいろいろとつじつまがあう気がします。やはり邪馬台国は北部九州だと思えてきます。(※あくまでも僕の予測ですよ。)
そしてなにより、このあたりには吉野ヶ里遺跡もあります。

▲ 吉野ヶ里遺跡から出土した棺
邪馬台国は家が七万戸あったと書かれています。他の国々は千戸ぐらいと書かれています。つまり、他の国々より特別に大きかったということです。なので、佐賀県東部から大分県西部ぐらいの一帯を邪馬台国としていた可能性も考えられると思います。
しかし、これでもまだまだ魏志倭人伝と一致しない部分もあります。今後、正確な位置が解明されるのかどうか分かりませんが、いつの日かとんでもない発見があることを期待したいと思います。
【参考文献】
・Wikipedia魏志倭人伝
・魏志倭人伝|邪馬台国の会
・『隋書』倭国伝
売り上げランキング: 139,491